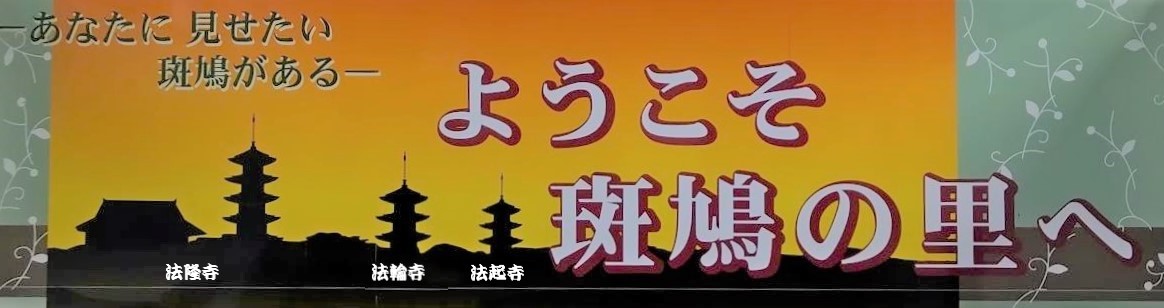- 投稿 2021/05/27更新 2021/05/27
- ニュース - 01.斑鳩町内ニュース

2021年5月20日の日本経済新聞に
という記事が載っていました。
中宮寺は現存する最古の尼寺
中宮寺は聖徳太子ゆかりの現存最古の尼寺です。
飛鳥時代の創建時は東に500㍍ほど離れた場所にありましたが、室町時代に現在地に移され、江戸時代からは宮家の皇女を迎える門跡寺院となりました。
中宮寺跡は整備されイベントなどに利用しています。
中宮寺は法隆寺夢殿の北東角にあり、同じ敷地内で砂利を踏んで閑静な庭を進むと、ヤマブキの植え込みの中に銅ぶき屋根の勾配が見えます。
中宮寺本堂の再建
中宮寺本堂は、1968年故高松宮妃喜久子さまの発願で、耐震耐火を施した鉄筋コンクリート造(RC造)に建て替えられました。
その設計を任されたのが、近代数寄屋建築の名手、吉田五十八でした。
本堂は浅い池に囲まれ、水の中から伸びる円柱が深い軒を支えています。
平安時代の寝殿伽藍を模し、浮御堂をイメージしてつくられました。
しかし、建設から半世紀余りがたち、2020年秋から老朽化した柱などの修復を行っており、2021年春、竣工当時の優雅なたたずまいが蘇りました。
中宮寺本堂を建てた吉田五十八とは?
1894年、「太田胃散」の創業者、太田信義の第8子として東京日本橋に生まれました。
東京美術学校(現在の東京芸術大学)で建築を学び、卒業後、ドイツの新しい建築をじかに見ようと欧米へ外遊しました。
そんな吉田五十八が衝撃が受けたのは新建築ではなくイタリアの初期ルネサンス建築でした。
「そこで生まれ、そこの血をうけた人間でなければ建てられない建築がある」と痛感した吉田五十八は、帰国後、若い建築家がこぞって近代建築に向かう潮流の中で日本建築の革新を志します。
「いまの日本建築は、ただ祖先の遺産にすぎない。それを、自分の資産に引き戻さなければならない。いままでの伝統的日本建築に近代性を与えることによって、新しい感覚の日本建築が生まれるに違いない」(「数寄屋十話」)
竣工当時、吉田は建築誌にそう書き残しています。
吉田五十八の建築作品
・1970年の大阪万博の松下館
中宮寺本堂を真似て作られた。
中宮寺の写真をみた松下幸之助が吉田に設計を依頼しました。
・大和文華館
・岩波書店の創業者、岩波茂雄が熱海に建てた「惜櫟(せきれき)荘」
・東京・築地の料亭新喜楽
中宮寺本堂の修復費用はクラウドファンディング
本堂は文化財に指定されていないため、国や自治体から修復の補助金が出ず、費用は日本経済新聞社運営クラウドファンディング(約1,000万円)や寄付で集めました。
朱色だった外壁や柱は竣工時の写真などを確認しながら茶系の落ち着いた色合いに復原され、杉板に和紙を貼った内陣の壁も新しくなりました。
修復を請け負った大林組は「RC造ながら、自然の空気の流れを利用した換気システムを採用するなど数寄屋造りを現代によみがえらせた建物です。随所に吉田五十八のこだわりが感じられます」と言っています。
日本経済新聞より引用